「九条の会・わかやま」 183号を発行(2012年2月7日付)
183号が2月7日付で発行されました。1面は、第4回「九条の会」全国交流集会に参加して ④、『第4回九条の会全国交流集会報告集』 事務局長・小森陽一さんから普及の訴え、九条噺、2面は、特別分散会での報告、国民投票法の検討状況 とりまとめ指示 「投票権18歳に引き下げ」今国会提出へ です。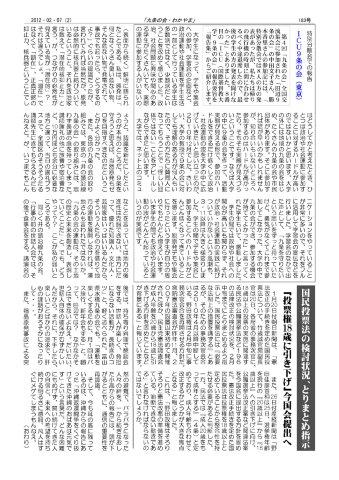

-
――――――――――――――――――――――――――――――
第4回「九条の会」全国交流集会に参加して ④
2011年11月19日に東京で第4回「九条の会」全国交流集会が開催され、「田辺9条の会」から中田文子さん、勝本香里さんが参加されました。詳しいレポート(参加記)を送っていただきましたので、4回に分けてご紹介しています。今回は4回目で最終回。

参加しての感想
勝本香里さん
戦争・原爆被爆と平和憲法9条、そして原発事故。どうする生活の実態と補償、等々、複雑にからみ合った多くの問題、課題が話された。
そもそも、参加させて貰おうと決心したのは、3・11の東日本大震災にある。未曾有とはいえ、自然災害に対する怖さはあるが、やむを得ない。いつかは復興できると信じている。しかし、簡単に治まらないであろう原発事故は人為災害であるはずなのに、これまで一度として、「この流れは間違っていた」と謝罪する人がいない。いったいその責任はだれに? それを明らかにしないまま、まだ続けようという体制でもある。それを良しとしてきた日本の社会、その上に重ね重ねして、幸せを求め、急速に発展させてきた私たちの生活・・・などと考えていると、やるせなくなる。何か意思表現しなくてはとも思っていた。だから、責任を感じながらも参加をさせて貰うことにした。沢山の報告で、頭の中は飽和状態となり、重い課題に心中重苦しかった反面、十分に勉強させて貰って充実感を味わった。こうして、報告書を書かせて貰うことにも深い意義を持つことになった。
飛行機に間に合わせて、私たちは少し早く会場を出た。急いで電車に乗り、羽田に向かった。東京を離れるときの街の光は雨の中に煙っていた。
中田文子さん
今回の交流会で印象づけられたことは、なんと言っても、原発と憲法9条は相容れないということが鮮明に語られたことである。私は、原発は「何となくうさん臭い危ない物。そんな危ない物で発電されて、事故でも起こったら、どうするのよ?」ぐらいの認識だったが、言われてみれば当然だが、原発は必然的に核兵器と結びついているということ。それを政治家は敢えて「潜在的核抑止力」と言う。が、つながりの必然性が見えている物が「潜在的」? それは違うでしょ。「潜在」ではなくて「顕在」、正真正銘の抑止力、核兵器ということでしょうと、認識を新たにしたというのが本当のところだ。9条を守ろうと思えば、当然原発もゼロを目指すべきなのだということがよく分かった。
また、各地の九条の会の取り組みでは、東京の「井の頭沿線九条の会」の取り組みには、思わず羨望の念を持ってしまった。講師謝礼の他に旅費や宿泊費など、10万円ほども余分に必要な地方と違って、当日の謝礼プラスαで、全国区のそうそうたる講師先生にきてもらえるんだもんねえと。が、いつまでもこんなことを言っていては地方の後進性は克服できない。地方にだって、優れた知識人・文化人・芸術家はいっぱいいるんだから、そういう人たちの力を借りて地方の運動を展開しなければ。澤地さんも言われたではないか。「九条の会の運動は、その土地の歴史と未来を創造し、表現していくことだ」と。でも、どうやって?? ここが私の弱いところである。
同じく井の頭沿線九条の会。「行事の前の世話人会では、その後で食事会をする。講演会の後では、持ち寄り料理で懇談会をする。世話人が楽しく、負担にならない活動が、長続きのコツ」と、軽く述べられた。富山県水橋九条の会でも、「運動を楽しくするために、月1回はバス旅行。新年会もする」と。翻って、田辺では? なかなかそうはできないよねえ。だいたい、世話人自体の確保がむずかしいんだから。それに、下手したら、楽しいことばかりの追求で、肝心の課題がおろそかになったりして・・・。
また、福島原発事故による突然の避難で、バラバラになった人々の絆を、一から紡ぎなおした小高からの報告には、頭が下がるとともに、通信の重要性を再認識。
そして、今も耳の底に残っているのは、沖縄からの報告にあった「沖縄返還闘争をくぐり抜けてきた沖縄のおばあは元気です」という言葉だ。どんな困難にもめげず、闘い続けてきた人の自信と、未来への希望を持ち続ける明るさに感服。凡人はすぐにメゲてしまうもんねえ。(おわり)
-
----------------------------------------------------
書籍・DVD紹介『第4回九条の会全国交流集会報告集』
事務局長・小森陽一さんから普及の訴え


「九条の会」のみなさまへ
日頃の活動に対して心から敬意を表します。
さて、去る2011年11月19日に東京で開催された「九条の会第4回全国交流集会」の報告集が、ようやく出来上がりました。
呼びかけ人である大江健三郎、奥平康弘、澤地久枝3氏の全体会での御発言は、「3・11」以後の「九条の会」の活動指針を明確にわかりやすく示しています。
全体会と特別分散会での発言は、呼びかけ人の言葉と響き合いながら「九条の会」の日常活動の多様な在り方を示し、読み応えがあります。各分散会の「まとめ」も教訓と示唆に満ちていて、大きく励まされます。
みなさんの会で、報告集をまとめて御購入いただき、「九条の会」の活動に生かしていただきたいと考え、一筆お知らせとお願いをさせていただく次第です。
今年の9月29日に開催する「九条の会講演会」(日比谷公会堂)の成功に向けて日常活動を活性化させ、報告集を多くの周囲の方たちに普及していきましょう。
事務局長・小森陽一
--------------------------
報告集 500円(送料別)
DVD 1,500円(送料別)
申込みは「九条の会」 mail@9jounokai.jp まで
-
----------------------------------------------------
【九条噺】
最近の朝日新聞掲載の川柳から2首紹介。「近頃は課税夫のノダと呼ぶらしい」と「宴席のつまみに古い珍味出す」▼後の句は、野田首相が施政方針演説でわざわざ福田・麻生両元首相の名をあげて、政策の基本はそう違わぬと述べたことを揶揄したもの。前句はテレビの人気ドラマをもじり首相の消費税増税策をチクリ。なにしろ野田首相、民主党幹事長代理の時に力説したのである。「マニフェスト、ルールがあるんです。書いてあることは命がけで実行する。書いてないことはやらないんです。書いてないことを平気でやる、これっておかしくないですか」(09年総選挙応援演説)。全くその通り。ところで、3年前の民主党のマニフェストにも消費税増税という文言はない。なのにいま大増税なんてやはりおかしい▼その野田首相が、〝失言〟連発の一川保夫氏に替えて田中直紀議員を防衛大臣に起用した。しかしこの御仁、前任者に負けず劣らず〝あやうい〟ときた。で、懸案の普天間問題もあり、就任早々沖縄県庁を訪れて知事と対談したが、「沖縄や石垣島には毎年伺っている。大体、水族館や硫黄島とかに出かけた」と語ったとか。仲井真知事は、さぞかし任命した首相への怒りを深めたことだろう▼俳優の高倉健さんも「国会中継を見て〝あれでよく務まるな〟〝恥ずかしいがなくなったのかな〟と思う」と嘆いている(1月30日・朝日)。このまま見過すことなんてとてもできないですね。(佐)
-
----------------------------------------------------
特別分散会での報告
ICU9条の会(東京)
第4回「九条の会」全国交流集会に参加された「田辺9条の会」の中田文子さん、勝本香里さんの参加記には、「特別分散会では8人の方の発表があったが、私たちは帰りの飛行機の時刻に間に合わせるべく中途退席したので、最後の学生の方の発表を聞けなかった」とありました。8番目の「ICU(国際基督教大学)9条の会」の報告要旨を「報告集」からご紹介します。
------------------------------------------------
大学生になって、デモや集会への参加、学習会の企画など、政治運動や社会運動を学生生活の一部として行っている学生は多数派ではなく、少数派だということを改めて感じました。政治、社会問題に興味や関心のある学生がたくさんいても、実際の運動に参加する人がいないのはどうしてかと考えたとき、ひとつは政治や社会運動に参加することに対するハードルが高いのではないかと思います。大学の外には地域の九条の会をはじめ、たくさんの九条の会や市民団体があります。そこに参加すれば話が早いのかもしれませんが、知り合いもいないところへ参加するのはハードルが高かったり、そもそも実態が見えづらいということです。ならば大学の中に9条の会を作って、活動実態が見える形で、参加のハードルをできるだけ低くして政治・社会運動の波を大学の中に広げていきたいと思い立ったのが、2010年12月でした。さいわい、大学の教授で9条の会に対しても理解のある方が何人もいたので、その方たちに賛同人になってもらうことで「怪しい団体ではない」ことをアピールしながらできたと思います。
大学では、ネット上のコミュニケーションをやっていることが非常に多いので、それをフルに活用して学習会の宣伝などを行いました。学習会のなかで出た声として、「九条を守りたいという思いをずっと持っていたけど、勇気がなくてこれまで参加してこなかった。大学の中で九条の会ができ、参加する機会が持ててよかった」と言ってくれた学生もいて、感動しました。
学生の間では政治や社会への関心が高いにも関わらず、それが政治・社会運動の実践に結びついていかないという風潮も、3・11以降は大きく様変りしました。学生の間でデモや集会に参加することへのハードルがどんどん低くなってきていることを感じます。脱原発デモや集会に行ったという学生が自分の周りでもどんどん増えています。いま学生の間でも政治や社会運動の波がどんどん起っているというのが実感です。
-
----------------------------------------------------
国民投票法の検討状況、とりまとめ指示
「投票権18歳に引き下げ」今国会提出へ
1月20日付朝日新聞は、「憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、竹歳誠官房副長官は20日、各府省の事務次官に、18歳以上の投票の実施に関連する民法や公職選挙法など196の法律改正の検討状況を、2月中旬までにとりまとめるよう指示した。国民投票法には『必要な法制上の措置を講ずる』とあるが、そのための事務次官会合は2010年4月以降中断している。野田政権は2月中旬に事務次官会合を再開させる方針だ。衆院憲法審査会が昨年11月、2007年の設置以来初めて開催されたほか、民主党憲法調査会が成人年齢を20歳から18歳に引き下げる方針を固めたことなどが背景にある」と報じています。
また、26日付産経新聞は「野田佳彦首相は25日、選挙権年齢を現行の『20歳以上』から『18歳以上』への引き下げに向け、公職選挙法改正案など関連法案を今国会に提出する方針を固めた。憲法改正手続きを定めた国民投票法は投票権を18歳以上と定めていることから整合性を持たせる必要があると判断した。一方、民法では『成人20歳をもって成年とする』(4条)と定めており、成人年齢も合わせて改正するかどうかが大きな焦点となる」と報じました。
これは、「野田政権はそろりそろりと憲法改悪の準備を進めている。油断できない動きである」と言わなければならないのではないでしょうか。
-
――――――――――――――――――――――――――――――