「九条の会・わかやま」 211号を発行(2013年2月3日付)
211号が2月3日付で発行されました。今号は付録2面もあります。1面は、平和と安全への雲行きを怪しくさせている領土問題(小沢隆一氏 ① )、立憲主義の危機に反「壊憲」の幅広い連携を(水島朝穂氏 ②)、九条噺、2面は、言葉 「天賦人権説」、『週刊ポスト』が自民党改憲案の問題点指摘 しかしその主張は…?! 、<付録>は、「あなたのおじいちゃまはねぇ」(三木睦子さん) です。



-
――――――――――――――――――――――――――――――
平和と安全への雲行きを怪しくさせている領土問題
07年5月、当時の安倍首相は憲法改正国民投票法を成立させ、改憲を公約のトップに掲げて改憲に突き進もうとしましたが、7月の参院選で大敗し、9月に突然政権を投げ出しました。昨年末の総選挙で再び改憲派・安倍政権が発足しましたが、現在と07年当時を比較すると、9条や平和をめぐる現在の情勢には特有の難しさが浮かび上がっています。東京慈恵会医科大学教授・小沢隆一氏(「九条の会」事務局)が『月刊・憲法運動』に書かれていますので、その要旨を4回に分けてご紹介します。今回は1回目。
小沢隆一氏 ①

第一は、東アジアの平和を脅かす事態の多様化、複雑化である。
アジアにおける軍事的プレゼンスの維持を世界戦略の重要な柱と位置づけるアメリカによる普天間基地の国内代替施設の頑迷な要求、とりわけ辺野古地区への移設の固執、これに付き従う日本政府、その中での拡大抑止戦略の維持、オスプレイ配備の強行、「基盤的防衛力」構想に代わる「動的防衛力」概念の採用、「武器輸出3原則」の見直しなど、日米安保に由来する平和への脅威は枚挙にいとまがないが、金正日総書記の死去にともない金正恩体制に移行した北朝鮮のミサイル実験など従来からの不安定要因に加えて、中国による尖閣諸島の領有権の主張の強まり(その原因の一端は、石原前東京都知事が仕掛け野田民主党政権が応じた国有化がある)、韓国による竹島の実効支配の強化など、領土問題をめぐる国際政治や国民世論の動向が、平和と安全をめぐる域内情勢の雲行きを怪しくさせている。12月の総選挙の直前にも、北朝鮮がミサイル実験を行い、中国当局の航空機が尖閣諸島周辺に侵入し、自民党の候補者たちの街頭演説も俄然ヒートアップした。中国当局の航空機・艦船の尖閣周辺での活動はその後も続いている。06~07年の時点では、安倍氏の復古タカ派的思想への期待は、きわめて熱烈にではあれ、ごく一部のタカ派言論人らの範囲に限られていた。彼の反中国の色彩が濃厚なナショナリズムは、財界などの支配層主流からはむしろ煙たがられていた。しかし、今回の再登板では、こうした周辺国の動きに対して硬軟織り交ぜた外交への期待が、より広範囲で共有されうる危険な状況が生まれている。これに意を強くしてか、安倍政権は、早々と、島嶼防衛などの増強のために、10年12月に民主党政権下で閣議決定された「防衛計画の大綱」の見直しと、「大綱」に基づいた「中期防衛力整備計画」(中期防)の廃止、防衛予算の11年ぶりの増額を決めている。(つづく)
-
--------------------------------------------------
立憲主義の危機に反「壊憲」の幅広い連携を
早稲田大学教授・水島朝穂氏が、HPに「憲法の危機とは何か―改憲か、壊憲か―」を書かれています。要約して2回に分けてご紹介しています。今回は2回目で最終回。
水島朝穂氏 ②
日本と比較し、ドイツでは何度も憲法を変えているという議論があります。確かに今年(12年)7月に59回目の基本法改正がなされています。でも、手続き的な規定が多く、重要な改正は5回ほどです。両院の3分の2以上の賛成は容易ではなく、与野党は相当議論します。3分の2から過半数に下げるという議論とは次元が違います。
今日の危機とは、このように改憲派から最も右の部分が分離し、「壊憲」派と結合した状況から生まれているのです。その彼らが衆参両院で3分の2を占めたら、それによりもたらされるのは、憲法の、権力に対する統制・チェック機能の解除、すなわち立憲主義の衰退に他なりません。
立憲主義というのは、一般にはあまりなじみがない言葉ですが、戦前は立憲政友会など「立憲」という語を冠した政党がいくつもありました。なぜでしょうか。あの足尾鉱山鉱毒事件で住民救済のため生涯を捧げた田中正造が、亡くなるまで聖書と大日本帝国憲法を肌身離さず持っていたという話はよく知られています。田中や自由民権運動の先達は、帝国憲法4条「天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行う」のなかに、天皇ですら憲法に縛られ、その「条規」によらなければ統治ができないという立憲主義の要素を見出し、権力と闘う武器としたのです。
その立憲主義がいま、揺らいでいます。私は、ドイツでナチスが権力を握った1930年代初頭の再現に近い危うさを覚えます。ナチスは28年の選挙では2.6%の得票率しかありませんでした。しかし30年の選挙で18.3%まで上昇するのですが、この選挙では16もの政党が乱立し、国民は失業と生活苦、混乱する政治にイライラした末、「はっきりものを言う」指導者に期待をかけていきます。そして33年3月の選挙の43.9%で全権を掌握し、11月にはナチスのみ出馬の選挙となるのです(得票率92.2%)。
「民意」はいつでもとりとめがないフワッとした存在で、時に暴走することを忘れてはなりません。一方で憲法は、つねに「時代に合わなくなった」と批判にさらされながらも、確固として変わらずにいるからこそ「民意」の移り気ぶりを浮き彫りにしてくれるのです。その憲法が、96条の改正によりフワッとした存在になった時、ドイツの経験が他国の歴史だけに留まらない教訓を示していることを知るでしょう。
現在問われているのは、従来のような「改憲派対護憲派」という図式ではありません。かつて自由民権運動を生んだような地方の保守層の間にも立憲主義の基盤は残っており、彼らは改憲派に与するとされてはいるでしょうが、必ずしも「壊憲派」ばかりではありません。96条の範囲内で改憲を主張するなら、立憲主義に踏み留まるという一点で、反「壊憲」の幅広い連携に加わる資格があるはずです。ナチス躍進を前にして、対抗勢力同士が互いに争って個別撃破されていった歴史の教訓も、また忘れてはならないでしょう。(おわり)
-
--------------------------------------------------
【九条噺】
先頃ノーベル文学賞を受賞して話題になった莫言氏(本名「菅謨業」55年2月生)が、北海道で13年間以上も逃亡生活を送って話題になった劉連仁氏(当会紙208号でも紹介)と同じ地方の出身で、莫言氏は劉氏と幾度か会っていたとか。莫言氏は劉氏の話をさらに詳しく知るために北海道・当別町を取材で訪ね、関係者らにも聞いてまわったという▼8年前、当別町で開催された歓迎・昼食交流会での莫氏のスピーチが残されている。莫氏は「劉連仁の北海道での日々は悪夢だったが、戦争による劉連仁の伝説は友好の象徴に変わった」「中国と日本は今、政治的に疎遠で、国民感情はお互いに親近感が薄らいでいるが、それは理性を失っているからだ。激高する感情を優しさに改めなくてはならない。それが新しい道を切り開く力になるだろう」と語った。まるで〝尖閣諸島問題〟等で揺らぐ今日をも見越したような発言だ▼他方、中国のサッカーチーム「杭州緑城」を監督として率いている岡田武史さんがインタビューで答えている(朝日新聞1月9日)「日本に帰って新聞を読むと中国はいやな国だな、と思うが杭州に戻ると、出会う大半の中国人からそんな感情は起きない」「普段の生活で嫌な思いをしたことは一度もない」「政治家でもない自分ができることは、中国人と日本人が心をひとつにしてプレーする姿をみせること」。スポーツ界に生きる人ならではの爽やかな発言だ。(佐)
-
--------------------------------------------------
言葉 「天賦人権説」
「自民党憲法改正草案Q&A」には、「人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました」と書かれており、「天賦人権説」を否定しています。
「天賦」とは「天が分ち与える」という意味ですが、もちろん神様が人権を与えてくれた訳ではなく、「人は生れながらにして人権を有する」ということです。日本国憲法は第10章「最高法規」97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定し、基本的人権の保障が憲法の最高法規としての役割であり、次世代のために人権を守る責任が我々にあるとしています(自民党案は97条を全面削除)。
「すべての人間は平等につくられている。創造主によって、生存、自由そして幸福の追求を含む侵すべからざる権利を与えられている(アメリカ独立宣言1776年)」「人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生れ、生存する(フランス人権宣言1789年)」「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である(世界人権宣言1948年)」と、「天賦人権説」に立っています。「天賦人権説」とは「人権は侵すことができない権利として保障する」という意味とも言えます。それを否定するのは、人権を制約し、戦前のような限られたものにしようとする意図であると言わざるを得ないでしょう。
-
--------------------------------------------------
『週刊ポスト』が自民党改憲案の問題点指摘
しかし、その主張は・・・?!
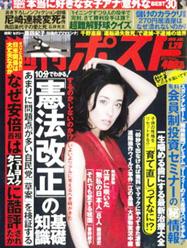
『週刊ポスト』(小学館)1月25日号は「自民党改憲草案『4つの重大問題』」を掲載しました。重大問題とは9条【戦争の放棄、戦力・交戦権の否認】、97条【基本的人権の本質】、21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】、92条【地方自治の基本原則】の4つです。

憲法改正は「『改正しなくてもできること』と『改正しなければできないこと』を峻別して議論しなければ国民がミスリードされる危険が生じる」とした上で、9条については、「『国防軍創設』に憲法改正は本当に必要か」と提起し、「自衛隊を国防軍に改称するだけなら自衛隊法を改正すればよく、憲法を改正しなければできないのは他国への侵略だが、それは自民党案でも禁じている。集団的自衛権による武力行使はできると閣議決定し、政府見解を変更すれば可能だ」と改憲派学者の主張を紹介し、「憲法改正しなくてもできる必要な安全保障体制の強化をまず実現すべき」と、集団的自衛権行使へ解釈改憲を主張しています。これはとても認められるものではありません。
97条については、「そもそも憲法は『国家権力から国民の権利を守るためのもの』か、逆に、『国家統治のために国民に守らせるためのものか』という憲法の立脚点を誤ってはならないはずだ」とした上で、「自民党改憲案では…基本的人権の由来を定めた97条が丸々削除された。代りに『全て国民は、この憲法を尊重しなれければならない』と国民の憲法擁護義務が盛り込まれている」とし、自民党案は「憲法が国民の権利を守るためのものでなく、…統治者の視点から国民の権利を制約する押しつけ憲法になっているのではないか」と、立憲主義に基づく正しい主張をしています。
21条については、自民党案には「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められない」が新設され、表現の自由を「憲法で規制しようとするのは、『民は知らしむべからず、由(よ)らしむべし』という、国民主権をないがしろにする亡国の発想である」と主張をしています。
92条については、「自民党案は中央集権化の固定化であり、憲法改正では一致しても、現在の中央集権体制をそのまま維持したい自民党と、統治機構の抜本改革をめざす維新やみんなの党とは方向性が正反対なのだ」と主張し、維新やみんなの党の応援団が如き主張をしています。
『週刊ポスト』の主張は一部賛成できますが、現憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という3原則を徹底して守るという首尾一貫したものではなく、「重大問題」も含む主張だと言わねばならないでしょう。
-
--------------------------------------------------
<付録>
「あなたのおじいちゃまはねぇ」
改憲派・安倍晋三氏が首相に返り咲きました。安倍氏というと母方の祖父・岸信介ばかりが出てきますが、父方の祖父は一向に出てきません。昨年8月に亡くなった「九条の会」呼びかけ人・三木睦子さんが、07年6月9日に父方の祖父・安倍寛のことを話されています。安倍首相に、改憲に血道をあげるのではなく、祖父・安倍寛の思想・行動を少しは学んでほしいとの思いを込め、ご紹介します。(DVD「三木睦子さんの志を受けついで・九条の会講演会」(12・9・29)の付録より)
三木睦子さん

皆さん、御機嫌よう。多分初めてお目にかかる方ばかりだと思います。今日はずいぶん大勢の方にお集まりいただいて、ありがとうございます。私は昔の育ちで、「女の癖に立ってものを喋るなんてことはけしからん」という時代に育っておりますので、家の中では大きな声をあげて喧嘩もするのですが、こういうところへ来てお話することには慣れておりません。聞こえにくかったら前へ出て来ていただきたいと思います。私は、来月で90になります。皆さんのような新時代の方たちにお話するのには、ちょっと話が古すぎるかもしれません。古いだけじゃなくて、少し抜けているところが多いと思いますけれども、お許し下さい。
今日は、昔、私の親しんだ方のお話をしようと思って伺ったわけでございます。昔々、われわれ日本人は戦争をしておりました。周り近所に背を向けて戦争していた。それで、なんとかして平和を取り戻さなければいけないというのが、私の夫やそのお友だちの意見でございました。
一所懸命平和を唱えておりますと、官憲の目が光って、特高警察なんていうのが後を付け回すんですね。それで、それをまいて、真夜中になってから家にいらしで、こそこそっと握り飯などを食べて、また、闇の中へ消えていくというようなお友だちもございました。でも私は、数少ないそういう平和を願うお友だちは非常に大事にしなければいけないと思って、真夜中でも急いで何かお腹にたまるものをと心掛けていたものでございます。本当に、本当に苦労して一所懸命に平和のために働いている方が多ございました。
いま総理大臣をやってらっしゃる安倍さんのおじいさまの安倍寛さんという人も、本当に熱心に平和を説いていらしたのです。
でも、安倍晋三さんが総理になるとすぐにその系図が出ましたけれども、安倍家の方は一つも書いてなくて、お母さまのお里のことばっかり。岸家の孫だとかなんとかって書いてあるんですね。私にとっては、どうも何かが足りない。反対なんじゃないか、やっぱり、安倍さんの息子さんなのだから、安倍さんのお父さま、おじいさまのことをもっと語るべきではないかと思ったわけでございます。けれども、新聞はそれを書きませんでした。そうなったのは、発表がなかったのではないかと思います。新聞社の人は、そんなに嗅ぎまわってものを書こうという態度ではない、発表されたままを書く―――ということは、安倍家の方はもうご先祖ではなくて、岸家だけがご先祖として堂々と繋がっているという感じだったのかもしれません。
でも、私は、いまの安倍総理のおじいさまと親しゅうございました。仲良しにしていただいておりました。というのは、あの方は一所懸命平和を説かれたのです。日本中で、こんな戦争してはいけないのだ、平和でなくではいけないのだということを一所懸命説いていらっしゃいました。特高警察などが後を付け狙って、演説会では何かっていうと、「弁士注意!」なんて大きな声をお巡りさんがあげるんですね。でも、そんなことをかまっちゃいないで、一所懸命、一所懸命、大衆に向かって、いま日本はどうあるべきかということを説いていらした安倍寛さんという人の姿を思い浮かべます。
背がすらりと高くって、あんまり肉付きはよくなかったのですけれども、がっちりした体つきの方でございました。安倍寛さんには奥さまがいなかった。だから、ご自分のお家へ帰っても誰もいないから、夜遅くなって、「ああ、お腹すいた。奥さん、頼む」なんて言って入ってらっしゃるんです。私のところにいらっしゃれば、すぐ三木が迎えて、二人で非戦論を語ることができるということで、よく来てくださったのですね。三木と二人で戦争をしないためにはどうしたらよいか、この戦争を避けるためにはどうしたらよいかということを相談しておりました。
歳にすれば私と安倍さんは、幾つくらい違ったんでしょうか、20歳ぐらい違ったのかもしれません。立派な安倍寛さんの話を聞いていると、おっしゃることはとっても判りやすくて、すばらしい方に思いました。立派なことをおっしゃっているなと思いながら、一所懸命聞いておりました。そして、少しでもあるものを取っておいて、明日いらしたら、安倍さんに食べさせたいと思ったぐらいです。
というのは、その頃はだんだん食糧が少なくなってきておりまして、なかなか美味しい牛肉も手に入らないし、新鮮なお魚も手に入りにくくなっておりました。少しでも栄養のあるものは、安倍さんのために、あるいは三木武夫のために、そして夜中にこそこそっと食事をして、また闇の中に消えていく人たちのためにとっておきたかった。私は歳が大分隔たっておりましたから、話が分かっているような、分からないような、なんでございますけれども、何かそうした方々のやることに共感を覚えるというか、敬意を表して、せめてなんとかしてお腹の足しになるようなものをと思って、一所懸命心掛けていたものでございます。
安倍寛さんはいつもなんにも不服をおっしゃらずに、食べたらすぐに、「さぁ行こう」と言って、また闇の中へ消えておしまいになりました。私は、ご苦労様だなあと思いながら、どうぞまた今晩、また明日っていうようにしてお見送りしたものでございます。あの方が、一旦口をついたら本当に凛々しくて、素敵な演説をなさっているのはよく分かっておりましたから、安倍先生のいらっしゃる時には、本当にできるだけのことをして差上げなければいけないと思っておりました。
安倍さんは奥さまもいらっしゃらず、孤独で一所懸命日本中を走り回って、国民のために、あるいは、将来の日本のために働いていらした人でございます。帝国議会の衆議院譲員でしたが、1942年の翼賛選挙では、三木と同じく翼賛政治体制協議会の推薦を受けずに当選し、当時の軍部主導の国会を厳しく批判してがんばられた方です。それを、いまの新聞社は何も書いてくれない。私はもう腹が立って仕方がありません。もっともっと新聞社の人がそこまで書いてくれれば、何も安倍さんの系図から岸家が抹殺されなくてもいい。おじいさまの安倍寛さんがこういう方だったということを、この平和な日本をつくるためにどんなにかご苦労なさったのだということを、書いてほしかったのです。
いまの私たちに戦争も知らない本当に平和な時代をつくってくださったのは、安倍寛さんだったと思うのですけれども、それを新聞は一つも書かない。私は新聞社の人は若いから何にも知らないんだ、どうしてこれを教えてあげる人がいなかったのか、と考えてみました。でも、いまや新聞社の社長だってなんだって、みんな戦後に生まれた若い人ばっかりなのですね。戦後60年ですから、そろそろもう定年退職しなければならない人たちが新聞社を支配している。それじゃどうにもならない。私は、少しでも声を大にして安倍寛さんのことを申し上げたい。でも、私もその頃は、ただ家の中の用ばかりしていて、安倍さんの実績もなんにも存じあげません。それでも、こういう人が立派な言葉で、国民のために平和を説いたことを、皆さまにも知っていただきたいと心から思います。
あの方は、本当に、姿形がそれは素敵な方でしたよ。背がすらりとしてほんとに素敵な人でしたけれども、姿形以上に、言動が本当に立派だと思いました。いいことをおっしゃる人でした。そして、決しておごることなく、毎日、足を棒にして日本中に平和を説いたのです。いまのこの戦争は、本当に日本人のとるべき戦争じゃないのだと、もっと平和でなければならないのだということを一所懸命説いていらした安倍さんの姿を思い起こします。
三木も一緒に一所懸命働いていたには違いないのですけれども、早く世を去られた安倍さんのことを考えますと、本当に残念に思われます。安倍さんのお子さんも亡くなり、お孫さんは天下を取って総理大臣になっていらっしゃるのに、おじいさまのことをご存じないのですね。生まれていなかったから、それは当然です。当然だからこそ、他人の私でも、声を大きくして、「安倍さん、安倍さん」って言わなければ、多分教えてくださる人ももう殆んどいないだろうと思うのです。安倍寛さんのことを思い描きながら、教えてあげなくてはいけないとしみじみ思うのでございます。
近々、私は大臣のお招きで――安倍さんのお招きじゃないんですね、あれは何大臣でしょうか、官邸へ行けることになっておりますので、その時にうまく安倍総理にお目にかかったら、「あなたのおじいちゃまはねぇ」って言って話をしたいと思うのでございます。
(2007年6月9日、「九条の会」学習会での挨拶)
-----------------------------------------------
安倍 寛(あべ かん)
1894年山口県大津郡日置村(現・長門市)に生まれる。東京帝国大学法学部政治学科卒業。「金権腐敗打破」を叫んで1928年の総選挙に立憲政友会公認で立候補するも落選。1933年に日置村村長に就任。その後、山口県議会議員などを経て、1937年の総選挙にて無所属で立候補し衆議院議員に当選。その後連続2期当選。いわゆる〝ハト派〟であり、第2次世界大戦中、1942年の翼賛選挙に際しても東條英機らの軍閥主義を鋭く批判、無所属・非推薦で出馬し当選した。戦後第1回の総選挙に向けて準備していたが、直前に心臓麻痺で急死した。(Wikipediaより)

(安倍寛)
-
―――――――――――――――――――――――――――――